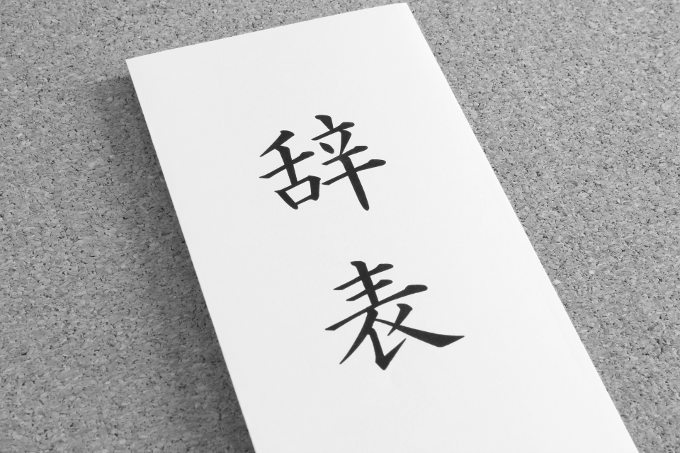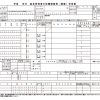退職していく社員から、退職後の健康保険について相談されることはよくあることである。
退職後のことだからと相談に応じず突き放すこともできるだろうが、退職したからといってその社員との関わりが全くなくなるとは限らない。取引先に就職するかもしれないし、私生活において関わることがあるかもしれない。
今後のことを考えると、仕事に支障をきたさない程度で相談に応じてあげたい。
退職後の選択肢
退職後の健康保険の選択肢は次の3通り。この中から、毎月納める保険料などを比較していずれに加入するか決めることになる。
- 「健康保険任意継続」にて会社と同じ保険に加入する
- 「国民健康保険」に加入する
- 「家族の健康保険」の被扶養者になる
もちろんのことだが、いずれを選択しても退職していく社員自身が手続きをしなければならず、手続きを怠ると無保険状態になってしまう。
健康保険任意継続
健康保険任意継続は、原則として在職中と同様の保険給付が受けられる。ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であって、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金は受けることはできない。
保険料は退職等した時の標準報酬月額によって決定されるが、在職中は社員と会社の折半で保険料を負担していたのが、任意継続被保険者になると全額自己負担になる。ただし、決定させる標準報酬月額には上限があり、保険料が必ずしも今までの2倍になるとは限らない。
また、任意継続被保険者として加入できる期間は2年間であり、原則としてこの期間の保険料は変動しない。
なお、任意継続被保険者として引き続き加入するためには、退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある必要があり、この要件を満たしていれば、退職日の翌日から20日以内に手続きをおこなうことで加入できる。
国民健康保険
国民健康保険の保険料(税)は、前年の収入等により計算されるため、退職後に無収入であっても、前年の収入等次第ではそれなりに保険料がかかり任意継続の保険料よりも高くなる。
ただし、倒産や解雇などにより退職した場合には、失業の翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を100分の30とみなして国民健康保険料(税)を算定する軽減措置が受けられるため、任意継続の保険料よりも安くなるケースが想定される。
国民健康保険料(税)は市区町村ごとに異なる基準で計算をされるので、任意継続の保険料と比較する際は、市区町村の窓口に問い合わせて保険料額をあらかじめ試算してもらうほうがよい。また、年度毎に前年の収入等により保険料が変動することも考慮しなければならない。
なお、国民健康保険に加入する場合、原則として退職日翌日から14日以内に手続きをおこなわなければならない。
家族の健康保険
退職後の年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者は年間収入180万円未満)などの認定基準を満たせば、家族が加入する健康保険の被扶養者になることができ健康保険料を負担せずに済むため、保険料でみると最も得する選択肢となる。
ただし、退職後に無職であっても、失業給付、傷病手当、出産手当金は収入とされ、受給日額が3612円( 60歳以上または障害年金該当者は5000円)以上になるときは、その受給期間については被扶養者として認められないため注意しなければならない。
なお、被扶養者の認定基準は保険者によって異なる場合があるので、事前に確認することを勧めよう。
無保険状態
退職した後、健康保険への加入手続きを怠ると無保険状態になってしまう。この状態で病院に行くと肥料費を全額自費で負担しなければならなくなる。
いずれの健康保険を選択するにしても、手続きに期限があるので注意しなければならない。